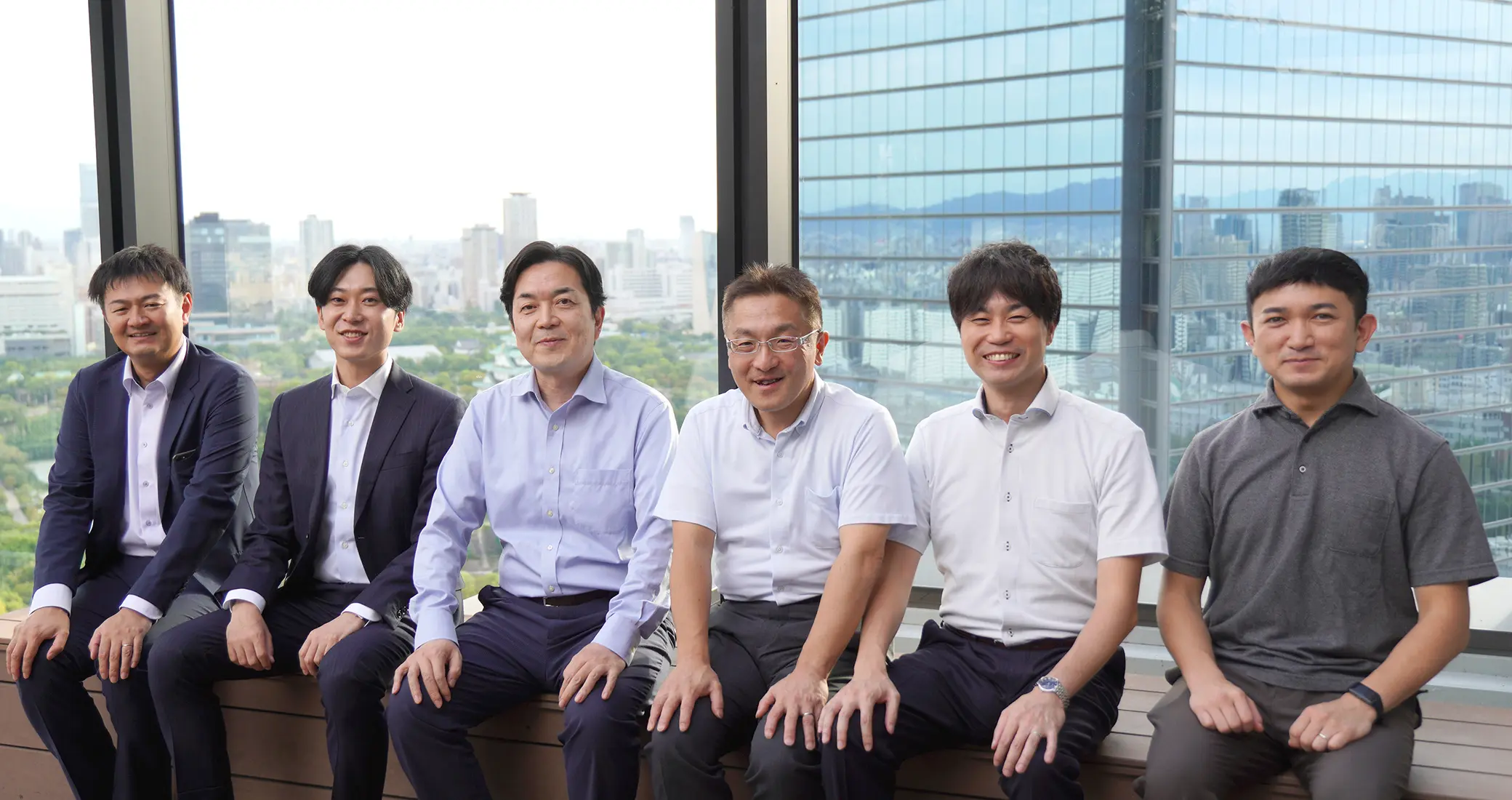「技術者不足」という社会課題に向き合う
---ネットワンとオプテージの共創プロジェクトはどのような経緯で始まったのでしょうか。
高橋 和宏氏(以下、高橋氏):当社は、社会基盤を支える情報通信インフラを提供しています。個人様向けには生活に密着したサービスであり、法人様向けにはビジネスの基盤を支えるサービスですので、災害時にもサービス提供が止まることのないよう、多くの技術者が支えています。しかし、将来的に技術者が不足するという社会課題を抱える中で、当社でも人材確保や業務効率化が重要な課題だと感じています。実際に技術者が不足するようになった時に、どのようにサービス品質を維持するかといった観点や、コロナをきっかけとした働き方改革により、テレワークを含めて働く場所に関係なく業務を継続できないかという観点で、最近ホットになっているデジタルツインの技術を活かして、当社が保有する多数のインフラ設備の可視化や活用を行う検討の熱が社内で高まっていました。

ちょうどその頃、嶋形さんからnetone valleyで開催されたイベントにお誘いいただき、そこでnetone valleyの施設紹介と併せて、デジタルツインのデモを見せていただきました。我々もデジタルツインの技術要素などは理解していましたが、デモ環境までは持っておらず、実際にデモを見せていただいたことで、これは何か当社でも役に立つのではないかと感じることができました。また、netone valleyはイノベーション創出を目的としているということもあり、我々の『技術者の業務を変えていきたい』という強い思いともマッチすると感じ、共創パートナーとして、一緒に新しい取り組みを始めませんかとお声がけしました。
---今回、ネットワンは共創の枠組みとして『netone Co-Creation』というプログラムを提供されました。オプテージの皆さんからの期待に対して、どのように応えようという思いがあったのでしょうか。
平山 大志:当社は、デジタルイノベーションを推進するため『ネットワークの力で、世界に創造力を』というコンセプトを掲げています。これを実現するには、当社自身がネットワーク分野以外の知見を蓄積すること、そして、多くの企業や人々と互いの強みを持ち寄り、共に新しい価値を創っていくことが重要だと考えています。オプテージ様の持つ電気通信事業者としての業務知見と、当社が持つデジタルツインに関するアセットなどを持ち寄ることで、技術者不足という日本の社会課題の解決に貢献できるのではないかと考え、共創プログラム『netone Co-Creation』を活用したプロジェクトの立ち上げを提案しました。

---オプテージの皆さんから見て、ネットワンの先端技術への取り組みについてはどのような印象を持たれていますか。
松木 浩平氏(以下、松木氏):ネットワンさんは、通信機器に詳しいベンダーとして、以前よりお付き合いさせていただいていました。通信機器に関する技術力には信頼を寄せていましたが、通信機器の分野に特化した会社というイメージが強かったのが正直なところです。今回、デジタルツインの取り組みや、netone valleyという設備も含めて、今までの分野から大きく飛び越えた新しいことを積極的に取り組んでおり、先進的な会社だなという印象を受けました。

デジタルツインに関しても、それをリアルタイムに運用するためのネットワークだけではなく、アプリケーションのレイヤーまでデモ環境を構築し、深く理解したうえで運用されていたので、今までの通信分野における信頼性が広く培われているなと感じています。
現場の課題をアイデアに
---今回の共創プロジェクトでは、どのようなステップを踏んでプログラムを進めたのか教えてください。
嶋形 直樹(以下、嶋形):2024年2月に両社でキックオフを開催してから計3回のワークショップを開催しました。プロジェクトの体制としては、両社共に複数部門から年齢や役職問わず参加者を選出し、両社のメンバー混同で2チームを編成しました。ワークの流れとしては、各チームでテーマに関するありたい姿の合意を形成し、その実現に向けた課題の洗い出しとアイデアの創出を行い、両社の決裁者に向けて成果発表会を開催しました。

我々の観点から見ても、従来の案件以外で会社対会社のリレーションを深める貴重な取り組みになったのかなと感じています。
---2チームに分かれてワークを進めたとのことですが、それぞれどのような課題解決に取り組まれたのか教えてください。
西馬 荘一朗氏(以下、西馬氏):私が取りまとめを担当したチームでは、電源設備や通信局舎といったファシリティを担当するメンバーが多く参加していました。彼らの業務をヒアリングしたところ、通信局舎の設備増強の工事を行う際、事前に図面を確認してこの辺りのエリアに設置できそうだとある程度のあたりを付けるのですが、図面の精度は完璧ではないため、結局のところ現場に行って実測しないと判断ができないケースが多々ありました。また、図面では2Dの情報しか得られず、現場に行くと図面に載っていなかった柱があったり、思ったよりも狭かったということもあり、どうしても現場に行って判断しないといけないのが実情です。しかし、工事設計の度に現場に行くのは大変ですよね。そういったところを踏まえて、センサーやカメラを活用して、デジタルツインにリアルタイムデータを反映させることで、現場の状況をリアルに遠隔からでも把握できるようになると、わざわざ現場に行かなくても工事設計がスムーズに進められるのではないかと考えています。また、精緻なデータが取れるようになることで、空調のエアフローなどシミュレーションが可能になる未来も目指すべき姿として、ディスカッションを進めていました。

---それが実現できると、技術者の業務効率化や働き方改革も進みそうですよね。西馬様のチームではフィールドワークも行ったそうですね。
嶋形:私を含め、当社のメンバーもワークに参加していましたが、オプテージさんの業務内容はそこまで理解できていなかったこともあり、通信局舎の見学をご提案いただきました。実際に見学に行ったことで、業務内容やオプテージの皆さんがおっしゃっていた課題を腹落ちさせることができ、さらにディスカッションを深めることができました。
---もう一方のチームはいかがでしたか?
松木氏:私が取りまとめを担当したチームでは、電源設備に関連する課題解決を目指してディスカッションを進めていました。電源のメンテナンスやテストは、片系ずつ電源を停止して作業を行いますが、片系だけ停止させるつもりが実際には両系を停止させてしまうという作業ミスが発生する可能性もあります。我々は通信インフラを担う会社ですので、両系の電源を落とすことで通信が停止してしまうと、場合によっては人命に関わる重大な影響を与えることがあります。そのため、この作業は非常に慎重に行う必要があります。これまでの作業方法としては、作業構成図をもとに作業者が頭の中で慎重に計算しながら実際に作業を行っていました。しかし、構成が複雑になると、その連動を把握している人でないと作業ができず、作業者の精神的な負担も大きくなってしまいます。そのため、いきなり本番作業を行うのではなく、テストを行ったうえで実際に手順に落とし込むことができたらいいよねという話が挙がり、それを実現するためのアイデアを考えていました。
---経験を積んだ人しか作業ができないと属人化してしまいますよね。
松木氏:そうですね。前段の話にもありましたが、技術者が減っていく中で、新しい人に技術を継承していかなければならず、ベテランだけに頼るのは難しくなっていきますので、デジタルツインを活用して技術者の作業負荷を減らすことができればといいなと思っています。
---実際にワークショップに参加されて、何か印象に残っていることなどありますか。
松木氏:当社からは三部門のメンバーが参加していたのですが、普段部署間で話すことってほとんどないので、同じ会社ですけどはじめましての人が集まって「デジタルツインで課題を解決しましょう」と言われても難しいですよね。相手の部署はどのような業務を担当していて、何を大事にしているかほとんど知らないので。そういった踏み込んだ話をするために、ネットワンさんのファシリテーターが話しやすい雰囲気や環境を作ってくれたのが大きかったかなと思います。
また、よくあるパターンとして、集まって課題を出すことはできるのですが、そこで終わってしまうことがとても多い。『netone Co-Creation』の良かった点は、課題を出すだけで終わりではなく、それを解決するソリューションまで一気通貫でご提案いただけたことです。さらに、一つのソリューションだけだと不足してしまう部分は、生成AIを活用した他のソリューションも組み合わせて、トータルに解決する方法をご提案いただき、改めてネットワンさんの目利き力の高さを実感しました。
人の繋がりでイノベーションは創出される
---最後に、今回の取り組みへの評価と今後の展望についてお聞かせください。
西馬氏:ネットワンの皆さんが親身になってプロジェクトに参加していただいた姿がとても印象深かったです。自身の課題を解決するために我々が一生懸命になるのは当たり前ですが、ネットワンの皆さんも自分事のように問題点の指摘やアイデア出しを行っていただきました。先程、通信局舎の見学に行ったという話がありましたが、通信局舎はふらっと行けるような場所ではないので、電車を乗り継ぎ、炎天下の中、みんなで汗だくになりながら歩いたことを思い出します。そういった時間を経て、チームが一致団結することで、とても良い形で終えることができました。
松木氏:ネットワンさんの印象が変わった、この一言に尽きると思います。今まで、設備のリプレイスなどでは最初に頭に思い浮かべる事業者さんでしたが、netone valleyの環境や今回の取り組みを通じて、今後、最先端ソリューションで何かやりたいと思った時にも、真っ先に頭に思い浮かべると思います。
高橋氏:今まではビジネスの関係で、工事の支援やソリューションの提案を依頼していましたが、今回の取り組みでは、ビジネス度外視で新しい価値を一緒に創ろうと、参加メンバー全員が同じ熱を持って取り組むことができました。とは言え、最初からその熱が高かったのかというとそうではありません。ネットワンさんのファシリテーターに参加メンバーの距離を縮めていただいたことによって、会社の文化を越えて意見をぶつけ合うことができ、次第に熱が高まっていったのだと思います。
今後の展望としては、まずは形にすることが重要かなと思っています。形にして触ってみることでアイデアを発展させ、5年後もしくは10年後に社会実装できる状態を目指していければと考えています。
藤田 大作氏:当社は若い社員が多いのですが、将来の社会を背負っていくメンバーとして色々なことを学ぶとても良い機会になったと思います。会社、部門、年齢を問わず、様々な方が業界を越えた一つの目標に向かって議論を進めていく姿を見て、イノベーションには人との繋がりや人間力が大事だなと改めて実感しました。

今後も新しい価値を創造していきたいと考えておりますので、ネットワンさんとは共創パートナーとして引き続き色々と議論できればと思っています。